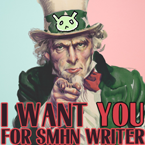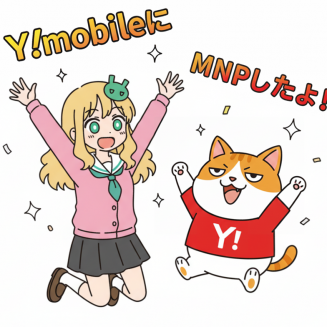Xiaomiは、以前より予告していた同社初の電気自動車、「Xiaomi SU7」シリーズをこの度、改めて正式発表、価格まで明らかにしました。
SUは「Speed Ultra」の略字で、Xiaomiの雷軍CEOは50万元以下の車で「最も見栄えが良く、スマートで運転しやすい車」を目指したと述べています。
XiaomiがEV開発を発表したのは2020年12月で、そこからたったの3年と少しで実車販売が実現したこのスピード感の速さには驚くほかありません。なお、実際には中国の北京汽車の傘下企業が製造を行うようですが、Xiaomiのロゴが記された工場があるようで、ここで研究開発だけでなく製造品質の検査なども行うとしています。FoxconnがAppleロゴ掲げてスマホ作っているようなものなので、ここはちょっと気になるところではあります。

Xiaomi SU7は走行性能やADAS(先進運転支援システム)の機能性によって3グレードを展開。最も安価な基本グレードは21万5900人民元で、これは日本円にしてたったの約460万円。それでいて、日本で560万円のテスラ Model 3に加速性能や航続距離で勝ります。
中間モデルのSU7 Proは24万5900元、日本円にして545万円ほど。Xiaomi SU7に比べてバッテリーを多く積んだ分加速性能は低下していますが、830kmを航行することが可能なうえ、上位モデルと同様に後述する高度な安全支援機能を搭載します。
最も高価なXiaomi SU7 Maxは、停止時から2.78秒で時速100kmまで加速することができ、これは日本で1300万円弱、同3.2秒のテスラ Model Sよりも高性能。こちらも価格は29万9900元で、およそ630万円ほど。中間はPro、最上位はMaxという命名規則がいかにもスマホメーカーっぽいですね。
総括して、Xiaomi SU7シリーズの価格は競合よりもかなり安価。ブランドが始まったばかりのバーゲン価格ともいえますが、レッドオーシャンと化しているEV市場で強い存在感を示せることは確かです。
センターディスプレイはEVの中でも比較的大柄な16.1インチを採用。ここで車内の多くの設定やエンタメの視聴が楽しめます。

一方で、アクセサリーとして下部にエアコンを調整するための物理ボタンを配置できるようです。走行中に温度や風量を変える際、正しい場所を触ったかどうかのフィードバックに乏しいディスプレイでは不便で危険という意見がありますが、オプションとはいえしっかり物理ボタンを残しているのは好印象です。

このほかにも、7.1インチメーターディスプレイやモデル限定の56インチ相当ヘッドアップディスプレイを備えます。さらに、後席向けにXiaomi Padを配置できるマウントも。これにタブレットを接続すると、自動車のシステムと密接に連携した機能が利用できるようになります。

また印象深いのがAppleエコシステムユーザーに向けた機能も用意されているところ。テスラ車ではApple CarPlayやAndroid Autoといったスマートフォンとの連携機能は用意されていませんが、Xiaomi SU7はApple CarPlayに対応。後席のタブレットマウントもiPadに対応し、車と連携できるとしています。

独自の音声モデルを搭載し、座席の位置やミラーの角度、さらにスマホを鳴らすことまで可能。アクセサリーも豊富に備えており、時間と速度を大きく表示できるダイヤルやイルミネーション、屋外用のBluetoothスピーカーなどを用意しています。

デザインも洗練されており、ヘッドライトの独特な形状がイギリスの高級車ブランドであるMcLarenのものに酷似している点以外は、特に気になる点はありません。ボディカラーはモノトーンで9色を用意。テスラのモデル3/モデルS(5色)や、BYD Seal(8色)を超えています。
シートなどのインテリアも紫をはじめとする4色から選択可能であり、こちらも選択肢が豊富で素晴らしいです。
価格のわりに性能が非常に良好で魅力的ではありますが、Xiaomi SU7が走っている姿を日本で見られるかといえばかなり厳しいでしょう。日本市場にスマートフォンを導入するのとは比べ物にならないほどの手間とコストがかかってしまいます。
Xiaomi SU7は発表後たった27分で5万台の注文があったようで、非常に良いスタートを切れているようです。先述の通り中国のEV業界は非常に混沌としたカオスな空間であり、中堅メーカーでも人員削減を行うところも出てきています。決して平坦な道のりではないでしょうが、Xiaomiにはぜひとも生き残ってほしいところ。