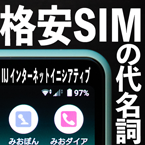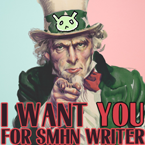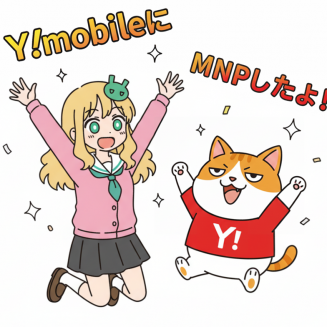先人たちがずっと夢見てきながらも、私たちの代でもまだ叶っているとは言いがたい、そんな夢のジャンルが「腕時計型のウェアラブルコンピューター」です。
驚くべきは、このジャンルのルーツは、1970年代までさかのぼれるということです。この時代には、ハミルトンウォッチカンパニーのPulsar Time Computer Calculator(1975)、ヒューレットパッカードのHP-01(1977)など、腕時計型コンピューターの元祖とも言えるデバイスが登場しています。

(Photo by watchuseek)
このような製品は、散発的に市場に登場しては惜しくも消えています。
2000年前後になると、PDA市場が盛り上がり、腕時計型PDAが熱心にリリースされるようになります。セイコーエプソンの「Chrono-Bit」、PalmとFossilの「WristPDA」がまさに腕時計型PDAの王道たるもの。他にもカシオが音楽プレイヤーやビデオカメラを内蔵した腕時計を発売し、NTT docomoも腕時計型PHS「WRISTOMO」を販売するなど、いくつかの試みがありました。
ですがPDA自体が下火となり、どれも定着せず、その多くが鳴かず飛ばずでした。
最近盛り上がりつつある製品群はどうでしょう。スマートフォンブームに牽引され、スマートフォンと連携し、さらにはそれ自体がスマートフォンと同様のOSを搭載するといったものが出てきています。
「世界初の本物のスマートウォッチです」
アップルの「iWatch」やサムスンの腕時計型デバイスが噂される中、そう豪語するのは、イタリアの「I’m Watch」です。なんとOSにAndroid1.6を搭載しています。公式サイトでも世界初を主張しています。
世界初かどうかはともかく、デザインは上々、未来的でもあり、非常におしゃれ。やや婉曲したディスプレイを採用しており、噂されている各社の製品に先駆けた試みですね。「I’m Watch」が登場したのは2012年のことです。
腕時計に様々な機能を載せるという試みはさかんに行われてきました。電卓、ストップウォッチ、加速度計、温度計、コンパス、GPS、カラーディスプレイ、スケジューラ、音楽再生機能などです。
しかしそれらは、ほとんどがスマートフォンでは既にできていることです。
だから、 スマートフォンを腕時計にしてしまえばいいという発想は、スマートウォッチを作る近道であり、AndroidをOSとして採用した「I’m Watch」はひとつの方法論としては正しいと思います。
さて、製品としての出来はどうでしょうか。
マニュアルは各言語でそれぞれ4ページ程度。日本語はありません。基本的には「わかっている人向け」と言えるでしょう。
「I’m Watch」はiPhoneなどと連携することができます。
電話帳の転送も簡単に行えます。iPhoneの受話器にすることもでき、着信時に挙動を選択可能です。「I’m Watch」自体にもスピーカーとマイクが内蔵されているからです。(品質は全くよくないです)
通知バーを引き下ろして、通知や設定が開きます。この辺はAndroidで見慣れたものですね。
「I’m Watch」には様々なアプリがプリインストールされており、画像の閲覧や音楽の再生、カレンダーの閲覧も可能です。
さらにTwitterやFacebookなどのソーシャルネットワークが楽しめます。それらのアプリを使うための設定などは、I’m IDを取得し、クラウド上から行います。「I’m Watch」は単体で文字入力ができませんから、各サービスのIDやパスワードの入力は、PCからクラウド上で行う形になるのです。
アプリケーションの追加もクラウド上から。
このように、PCやスマートフォンとうまく連携する、これからのスマートウォッチの方向性を示しているように思います。
ただ問題があるとすれば、とにかく電池がもたない、屋外での視認性がよくないということです。これはSONYのスマートウォッチMN2、LiveViewといった製品よりも悪いと感じます。あくまで趣味の域を出ないといった感想を持ちます。また、Androidとの連携もうまく行えませんでした。
しかし、重量感、婉曲したディスプレイ、質感、近未来的なデザイン、豊富なカラーバリエーションはとても惹きつけるものがあり、おしゃれな日常のアイテムとしては、非常にぐっとくるものがあります。多少背伸びをしてでも使いたくなると思いました。
発売直後、人気があったせいか、製品がイタリアから全然発送されて来ないといった声はありましたが、今ではexpansysさんでも購入可能なので、敷居はぐっと下がっています。
時計ではなく、ガジェットのひとつとして非常に個性的で、面白いデバイスだなと思いました。
情報元:en.wikipedia.org, watchuseek
機器提供:expansys