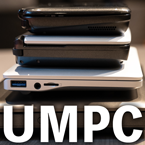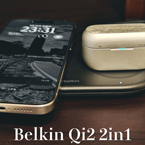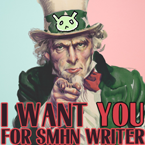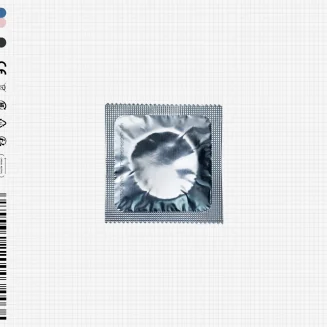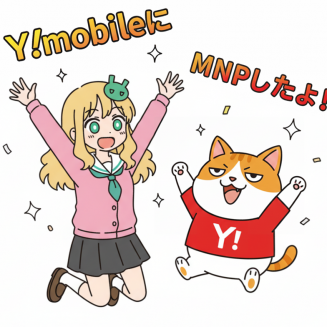優秀な入門機?
SwitchBotより「SwitchBot お掃除ロボット S20」を提供していただいたのでレビューします。ローラー式の水拭きモップ搭載機としてはかなり安価なのが魅力な製品に仕上がっています。
Index
セットアップは簡単、お手入れもラクラク
SwitchBot お掃除ロボット S20のセットアップは、同梱のクイックスタートガイドに沿って進めれば特に迷うことはありません。
ざっと流れを説明すると、ステーション、および床が濡れないようにする防水マットを設置したうえで、本体に貼られているシールを外してからサイドブラシを取り付け、本体の天板を外して主電源を入れ、ステーションにつなげれば大体完了。後はアプリでの登録作業です。
アプリのダウンロードからWi-Fi接続までの流れは、スマートホーム製品に慣れている方にはファームウェアアップデートを除き10分とかからず完了するでしょう。特にSwitchBot製品をいくつか買っているユーザーには、いつもと変わらぬ感覚で行けると思います。
しかし、ソフト面でのセットアップは簡単な一方で、ハード面では充電やゴミの吸い取りを行ってくれるステーションが「デカくて置き場に困る」という問題があります。これは後述します。
消耗品管理の親切設計
S20の便利な機能の一つが、アプリ内での消耗品交換時期の案内です。汚水フィルターやゴミフィルター、ゴムブラシに水拭きのローラーモップ、水切りワイパーなど、かなり多くの部品について使用時間を記録し、交換時期の目安を教えてくれます。
しかも嬉しいのが、個別の使用状況によって「あとどれくらいで交換・お手入れすべきか」を教えてくれるというところ。例えば筆者の場合、ゴミ掃除だけさせて水拭きしないこともあるためか、ごみフィルターの使用時間は7時間となっている一方で、水拭きのローラーモップは使用時間が3時間となっています。
モードごとの使用状況に応じて各部品の使用時間が明示されるため、交換時期の判断に非常に役立ちます。
メンテは滅多にしなくてOK、工具いらずでスピーディー
日頃、掃除させるのには手間はほとんどかかりません。部屋がロボット掃除機を動かせる程度に片付いているのは当たり前として、当然モップの洗浄も乾燥も全自動ですし、定期的なメンテナンスも、私の使用頻度であればそれほど頻繁ではありません。
実家にあった少し古い(がこれより高価な)ロボット掃除機だとモップの自動洗浄はついておらず、都度モップを取り外して洗っていたのでこうはいかなかったことを考えると、ロボット掃除機の進化って素晴らしい、という一言に尽きます。
いずれにせよ、掃除のことをほとんど考えなくて済むというだけでも、精神的な負担がずいぶん軽くなります。
ただし一点気になるのが、水拭き後、モップを乾燥する動作が4時間続くところ。この乾燥は当然ながら水拭き作業を行った後に発生するものですが、近くにいると割と耳障りです。乾燥を行う時間はモップの乾き具合によって変わる…ということはなく、常に設定された時間動作します。そのデフォルトが4時間というわけですね。
筆者の場合は、いつも出勤後に動作させているため問題はありませんが、在宅ワークの方だと動かす時間が悩ましいところですね。
さてこれまではロボット掃除機が自律的に行う掃除についてでしたが、ここからは人間がたまにやってあげるべき簡単なお手入れを試してみました。今回はモップの洗浄で用いた汚水を一時的に保管する汚水ボックスおよびダストボックスをお手入れしてみましょう。
いずれもドライバーなど工具は不要で、ダストボックスは本体上部のカバーを開けると出現し、汚水ボックスは本体後方のつまみを押しながら引き出せばOK。ダストボックスにはゴムブラシやモップのゴミを取り除けるメンテナンスツールがはめ込まれています。小さいだけに別途保管する形だと無くしてしまいそうなので、このやり方は非常に優秀ですね。

ダストボックスは上下をつまんで開けるとボックス内の掃除が、左側から開けるとフィルターを取り外すことができます。フィルターは取り出して水洗いしてから24時間乾燥させましょう。
そして、汚水ボックスは個人的に高頻度でお手入れをお勧めしたい場所です。というのもこの汚水、私がメンテナンスしたタイミングだと非常に臭く、雑菌やバクテリアか何かによる膜が張っているような状況となっていました。固形の銀イオンとかでも入れておけば改善するでしょうか?
仕組み的にこれらで掃除をしているわけではないとはいえ、あまり気持ちいものでもありませんし、使用頻度が低くともこまめに掃除しておいたほうが良いかもしれません。

掃除性能は及第点、しかしツッコミどころも
さて、肝心のロボット掃除機としての性能についてのお話です。最初に断っておくと、筆者は現行世代のロボット掃除機を触ったことがあるわけではなく、せいぜいかなり古いルンバと、2世代ぐらい前の某有名中国メーカー製が実家にあったぐらい。
よって他の製品と比べてどう、ということは言えませんし、言ったとしてもそれは不公平であるため、そういった比較は他の方に譲ることにします。
さて日頃の清掃についての評価ですが、ゴミの吸引と水拭き、どちらにもロボット掃除機の根幹にかかわるような致命的な問題はありませんが、いずれも壁際が弱いという弱点が露呈しました。まずは水拭き機能から紹介していきます。
先に擁護すると、ロボット掃除機は仕組み上壁際が弱いのは当然のことで、だからこそ各社サイドブラシを付けて対策しているわけですし、ヘタすれば30万円が見えてくるようなお掃除ロボット業界で、定価ですら10万円を切るSwitchBot お掃除ロボット S20は(水拭き対応モデルとしては)比較的安価なほうであり、いずれも価格のことを考えれば全く許せる範囲です。
まずは水拭きについて、「壁際が弱い」とする根拠をお話ししましょう。SwitchBot S20が一般の水拭き機能搭載モデルと大きく違うのは、冒頭にて一瞬触れた通り「常に洗浄され続けるローラーモップを採用している」というところ。

最近の水拭き対応ロボット掃除機の多くが「円形の回転するモップを2つ搭載している」タイプなのに対し、S20はローラー形のモップと、水切り用のワイパーを採用。これによって常に清潔なモップで水拭きができるというのがメリットなのです。
しかし、S20には結構大きな欠点が。それはローラモップのサイズ(幅)がそこそこに小さく、そして床面のすべてをカバーしようという工夫が見当たらないところです。
S20より後に登場した類似の機構を備える製品では、円形ではなく四角に近い本体形状にすることで幅広なモップを搭載したり、ローラーモップを壁際まで伸ばせる機構を用意したりしていますが、S20にはこれといった「壁際への対策」がありません。
下の画像は公式サイトからの借用ですが、S20の場合本体の径に対してモップ部分が全面をカバーしているわけではないので、必然的に壁際数cmは水拭きが届きません。

そのせいか、台所などでも端っこのほうの汚れが取れていないな?と感じたシーンはありました。記事執筆中にふと思い立って、キッチンペーパーに台所洗剤をしみこませて台所の壁際をツーっとなぞると、結構な汚れが付着します。ここはどうしても妥協せざるを得ないポイントではあります。
しかし、そもそものローラモップの構造がかなり精神衛生上良いというのは重要なポイントです。SwitchBot独自の「RinseSyncシステム」により、掃除中も常にモップに清潔な水が供給され続け、反対に汚水をワイパーで絶えず水切りしているため、汚れたモップで床を拭き広げることがないとしています。

汚水を水切りするワイパー。定期的にゴミを取るなどお手入れが必要そう
筆者としては、これからのロボット掃除機の水拭き機能の新しい形、それをSwitchBot お掃除ロボット S20(先代モデルのS10も)は先取りしていると思っています。何より偉いのは、ローラモップ式の機構を備える競合製品は、軒並み十数万円を超える高級機種であるということ。
一方で水拭きではない、本来のロボット掃除機の役目である吸引についても、やはり壁際に拾いきれなかったゴミがたまに散見されました。ただしこれは再度お伝えさせていただきますが、他のロボット掃除機との比較を経ているわけではない点にはご留意ください。
これも構造を考えれば当たり前のことで、先ほどもお話ししましたがロボット掃除機の中央でしか吸引できないからこそ、各社サイドブラシを付けてゴミを中央に掻き出そうとしているわけです。
しかし壁際のゴミ対策、これはかなりシンプルな解決方法があります。それは2往復させること。単純極まりない方法ではありますが、これで結構マシになった印象です。
しかしサイドブラシには1点ツッコミどころが。部屋の角にピッタリ本体を寄せたとして、サイドブラシは部屋の隅っこに接触することはできませんでした。これではゴミを掻き出す・出さない以前に、部屋の角は掃除すら行えない状況です。

まあどうせ人間も四角い部屋を丸く掃くものですし、ここは仕方ないものとしてあきらめました。筆者は古典的な昼ドラよろしく、姑になった気分で壁際や角を掃除して「あら、こんなところに埃が」と嫁いびりごっこをして楽しむことにしています。まあこんな隅っこのゴミなんて気づかないかもしれませんが。
スマートホーム製品メーカーだからこその連携が価値
SwitchBotのお掃除ロボットが他メーカーと大きく違うところ、それはSwitchBotが「スマートホーム製品を作っている」ということです。これによって他の製品と連携出来たり、ロボット掃除機があることを前提とした製品を用意したりすることができます。
他に類を見ない加湿器への自動給水で差をつけていけ
SwitchBot お掃除ロボット S20にはロボット掃除機ではまるで類を見ない激レアな機能があります。それは、自動給排水機構を活用した「加湿器への自動給水」です。
筆者の環境では活用するのを断念したためここで軽く触れるにとどめておきますが、洗濯機下などにおいてロボット掃除機への給排水を自動化する「SwitchBot お掃除ロボットS10/S20水交換ステーション」と、ロボット掃除機から水を受け取ることができる「SwitchBot 気化式加湿器 Plus」を用いることで、若干面倒な加湿器への給水すら全自動で行ってくれるようになります。もはや人間が加湿器に対してやることはフィルターのお掃除だけ、というレベルです。

とはいえこの水交換ステーション、ご家庭によってはかなり設置が難しいでしょう。このステーションは当然ながら給排水が必要であり、そのホースは主に洗濯機のホースから分岐させるようになっています。当然洗濯機の近辺に設置することを求められていますが、筆者宅の場合は洗濯機前は風呂場のマットが邪魔をして設置できませんでした。
また設置には前方1mのスペースを要求するため、洗面所がとても広い家庭か、逆にユニットバス構造のため洗濯機が洗面所に置けず、キッチンや廊下にあるようなご家庭でないと設置は難しいでしょう。

スマートホーム製品メーカーのスケールメリットを生かせる
SwitchBotが他のメーカーと違うところ、それは幅広いスマートホーム製品を手掛けているということは先ほどご紹介しました。先ほどの加湿器もそうですが、これ以外にも玄関ドアに後付けするスマートロックやスマート赤外線リモコン、電球やシーリングライトなんかも取り揃えています。
これによって役立つのが、各製品の連携のしやすさ。Google HomeやAppleの「ホーム」などに連携し、オートメーション機能を用いて連携することもできますが、声で動作できるのは「運転開始・停止・ホームに戻る」など、利用できる機能は大きく限られてしまいます。
しかしSwitchBot製品でそろえていれば、かなりきめ細かい自動化が可能ですし、音声アシスタントに頼らない操作も可能。
例えば「SwitchBot リモートボタン」を玄関付近に配置し、ボタンによって「すべての照明とカーテンを閉じる」という機能と「ロボット掃除機を動作させる」という機能をそれぞれ割り当てれば、出勤中によしなにお掃除してくれます。「スケジュール実行でもいいじゃないか」という意見もありそうですが、筆者の場合は毎日動かすわけではないので、これでちょうどいい感じ。

SwitchBot リモートボタン
筆者は常々主張しているのですが、スマートホームにおいて人間の操作方法を「声」だけに依存するのは、むしろ不便になるのでは?ということ。電気をつける、消すといった日頃おこなう定型的な作業は、いちいち同じフレーズを口にせず、ボタンをぽちっとしてやったほうがよほど便利なのです。
そしてこれは、例えばネットに疎い同居人や一人暮らしをする高齢者にとっても有効です。「このボタンを押したらロボット掃除機が掃除してくれるからね」と伝えるとかテプラで残して置けば、スマホいらずで操作が可能です。
それで言うと、SwitchBotさんにはもっと多種多様なボタンを出してほしいのですが、それは別の話。
とはいえ、「ロボット掃除機と何を連携するのか」と言われたらそれまでではあります。それこそ外出時に電気消して掃除を開始する、ぐらいのシナジーしかありません。後付けでドアを開閉自動化する製品の登場に期待したいところです。
本体とステーションのデカさ、どう付き合う?
SwitchBot お掃除ロボット S20の最大の弱点。それは「本体もステーションもデカいこと」です。
まずはステーションから。かつてのロボット掃除機のステーションといえば、その役割は充電程度なものでしたが、今やゴミの吸い取り、水拭き用の給水と汚水の受け取りにそれらの貯蔵、モップの洗浄と乾燥まで行ってくれます。
そんな高機能なステーションですが、それだけの機能を詰め込めば当然デカくなります。SwitchBot お掃除ロボット S20のステーションの寸法は幅38cm×奥行22cm、高さもしっかりあって46cm。
ちょっと伝わるか微妙ですが、ステーションはmicro-ATXまで対応するデスクトップPCケースのサイズにほど近いです。身長体重をりんごで表すキティちゃん的な計測方法を行うと、奥行きはエリエール1つ分、高さは7つ分ということが分かりました。

これに加えてステーションに待機中には本体ぶんだけせり出しているわけなので、結構スペースを取ります。当然、不安定なカーペットの上にステーションを置くのは禁止です。
そのうえ、公式では「左右0.5m、前方に1m」の空きスペースを要求します。廊下や部屋の端っこなど何もないところにポツン、と置くのがベストではあるのでしょうが、筆者の家、というか全体的に狭い日本の住宅環境でそれをやるのは非常にキツい。
筆者の場合、ピッタリ嵌まりそうなL字棚があったので、奥側に滅多に飲まない泡盛を、手前にステーションを置くことで対処。当然左右0.5mは満たしておらず、何なら前側1mもギリギリ未達な立地ですが、幸い帰還してもドッキングできない、という事態は一度も発生していません。

また、筆者宅ではそこまで気にはならなかったものの、本体そのもののサイズもご家庭によっては問題になるポイントかもしれません。
S20は直径365mm、高さ115mmというサイズ。高さは「ロボット掃除機対応!」と銘打った家具であればあまり大きな問題にはなりませんが、問題は幅。筆者宅のローテーブルでは高さこそ問題ないものの、テーブルの横側から進入しようとして突っかかる場面が幾度となくありました。同じくロータイプのソファはぎりぎりどの方向からも進入できるものの、進入できないと判断されたのか、たびたびソファ下回りを掃除してくれないことも。

S20とK11+比較。サイズをとるか水拭きを取るか……
さて、そうなると気になるのが小型モデルとの比較。ここで、今回レビューしているSwitchBot お掃除ロボット S20と、同時期に発売された新モデルのSwitchBot ロボット掃除機 K11+を実際に比較していきます。
余談ですが、S20のほうは「お掃除ロボット」、K11+のほうは「ロボット掃除機」です。SwitchBotの他モデルを確認したところ、水拭き機能があって掃除機の枠を超えたものを「お掃除ロボット」と呼称しているようですね。
SwitchBot K11+について軽く紹介しておくと、定価5万9800円ですが、セール時は4万9800円ほどで販売されている「世界最小級」を謳うロボット掃除機。全自動のゴミステーションがつくモデルとして、比較的安価なほうに入ります。

さて、まずはステーションのサイズから。紹介した通りS20はMicroATXのPCケースに近いほどのサイズ感ですが、K11+のステーションの底面はiPad Pro(11インチ)と同じぐらい、高さもiPad Proの幅(長辺)と同レベルと、かなりコンパクトにまとまっています。

なお、公式サイトではロボット掃除機含めた専有面積はA4サイズ以内、高さは500mLペットボトル程度と紹介されています。水拭き機能がなく、ステーションがする仕事が少ない分、とても小さい。これなら最悪、PCデスクの下だとかに置いて運用もできそうです。

幅はエリエール1つ分。高さはピエトロドレッシングより少し大きい程度。
次は本体。S20は直径36.5cm、高さ11.5cmである一方で、K11+は直径24.8cm、高さ9.2cm。面積が2倍以上違うので、実際に写真で比較するとK11+がかなり小さく見えます。

S20本体の取り回しについては既にふれたので省略するとして、S20ではそもそも進入できなかったり、機嫌次第で掃除してくれなかったりするソファやテーブルの下もラクラクにこなしてくれますし、キャスター付きの椅子の周りなども、結構入り込んで掃除してくれます。先述したテーブルの脚の間も余裕です。

なお、それでもK11+の高さについては注意が必要です。SwitchBot お掃除ロボット K11+の9.2cmという厚みは、ロボット掃除機の中では取り立てて薄いというわけでもありません。競合他社の似たような小型をアピールするモデルでも同様な傾向がみられるのですが、「小型」をアピールするモデルよりも、高級機種のほうが薄いです。
弊誌読者にわかりやすい例えであれば、「スマホよりタブレットのほうが薄くしやすい」的な感じでしょうか。そのため、ロボット掃除機を検討する際に厚みがネックになるご家庭であれば、薄さを謳う機種を選ぶべきです。
さて、肝心の掃除能力についてご紹介しますが、比較ができる吸引機能に絞っても一長一短という印象です。K11+は狭いところまでガンガン入っていける小回りの良さが魅力的である一方で、本体直径が小さい影響か掃除を終わらせるまでに時間がかかっていました。
S20はその巨体で掃除できない場所がある一方で、やはり一度の走行で吸引できる幅が広く、またサイズ分だけパワーがあるのか、回転や走行時のアクションがK11+比でテキパキしている印象でした。ただ筆者の環境では、実用的なシチュエーションかつ公平な条件で比較できなかったため、これらの掃除スピードはあくまでも筆者の主観に基づくものであることに注意してください。
そして、筆者のユースケース(約20㎡を2度掃除させる)では今のところ問題とならなかったのですが、K11+は小柄なぶんだけバッテリー持ちも良くなさそうだったのは留意すべきでしょう。同じ面積を掃除するのにK11+のほうが時間がかかるためか、作業終了時のバッテリー残量はK11+のほうが少なくなっていました。
今は新品同然なため、一通り掃除してもバッテリーが枯渇することはありませんでしたが、長く使っていくにつれてだんだんバッテリーがヘタって行くと、いずれ掃除の途中に力尽きて再充電が挟まる可能性もあります。筆者の実家のロボット掃除機も、それでだんだんと使い物にならなくなって修理or買い替えてきた歴史があります。つまりバッテリー容量と燃費は寿命に直結するというわけです。
ここまで比較した中で個人的な感想をお伝えさせていただくと、たいていのご家庭ではSwitchBot お掃除ロボット S20のほうが価格も勘案したうえでベターであると感じました。SwitchBot ロボット掃除機 K11+が実売5万円前後でS20が実売7万円強と、2万円ほどしか差がないのも大きいポイントではあります。
一方、K11+の本体とステーションの小ささは場所によっては強烈な魅力です。しかし両者の価格差は定価でも2万円という点を考えた時、本機の強みが活かせるような環境でないと推奨しづらいというのが本音です。その小ささが活きるような環境、例えば単身者向け物件の部屋、もしくは寝室や廊下程度で汚れづらい戸建ての2階部分を掃除するサブのロボット掃除機としては非常にお勧めできます。
総評
いくつか惜しい点はあるものの、このお値段でここまでの機能を実現しているのは非常に魅力的です。
SwitchBot お掃除ロボット S20の定価は9万1800円ですが、筆者が確認したところでは、サマーセールにて6万9899円、それ以外の定期的なセールでもおよそ7.1~7.3万円程度と、7万円前後が実質的な価格です。
類似するローラー式モップを備える競合製品はここ数か月で雨後の筍のように出てきましたが、いずれも高価。その代わりに、大抵の製品はSwitchBot お掃除ロボット S20の最大の弱点である壁際の水拭きを解決していたり、走行中のモップ常時洗浄に温水を用いていたりするものもありますが、定価はS20比で1.5から2倍以上にもなってしまい、おいそれと手が出せるものではありません。
そういう意味で、ロボット掃除機の初めの一台にも、水拭き機能を備えていないロボット掃除機からの買い替えの需要、そしてコスパを求める層にも、SwitchBot お掃除ロボット S20はお手頃な価格で応えてくれるものと思います。