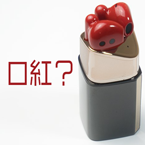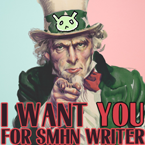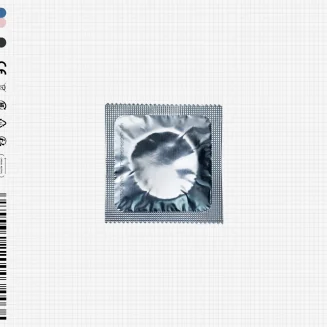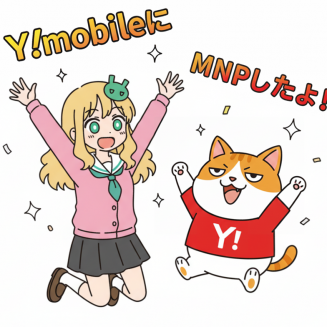米ニューヨークのハードウェア開発プロジェクトOddly Specific Objectsは、新型の電子書籍リーダー「Open Book Touch」のクラウドファンディングをCrowd Supply上でプロジェクトページを公開しました。
小型の電子ペーパー画面とタッチパネル、前面ライト、Wi-Fi/Bluetoothを備えた端末で、KindleやKoboといった大手メーカー製の電子書籍リーダーが「コンテンツを消費するための家電」であるのに対し、Open Book Touchは「自分でいじれるEインク読書端末兼開発ボード」という位置づけの、完全オープンソースのデバイスです。
本機は、その名の通りタッチ操作に特化した設計が特徴です。前世代機の「The Open Book」に搭載されていた物理ボタンを廃止し、4.26インチのE Ink(電子ペーパー)ディスプレイと静電容量式タッチパネルを採用。これにより、3Dプリント製の筐体を含めても厚さ1cm未満という薄型化を実現しているとのこと。
ディスプレイは4.26型のEインクパネルで、解像度は480×800ドット、画素密度は約219ppiです。7型クラスでよく使う解像度を小さな画面に詰め込む構成なので、文字は十分にシャープに表示できるといいます。
フロントライトは暖色LEDと寒色LEDをそれぞれ5個ずつ搭載します。明るさだけでなく色温度も細かく調整できるそうで、暗い部屋では暖色寄りの光にして目の負担を軽くする、といった夜間の読みやすさにも配慮しています。
心臓部には、IoT開発で人気の高いEspressif Systems社のデュアルコアマイコン「ESP32-S3」を搭載。フラッシュメモリは16MB、外付けSRAMは8MBで、EPUBファイルの解析など、そこそこメモリ負荷の高い処理にも対応できる構成です。Wi-FiとBluetoothに対応しており、単なる読書端末としてだけでなく、ユーザー自身がファームウェアを書き換えて機能を拡張できる「開発ボード」としての側面も持ち合わせています。
電子書籍の保存にはmicroSDカードを使う前提で、カード上のファイルを読み取る作りになっています。

ソフトウェアは、ESP-IDFとFreeRTOSの上に構築した独自ファームウェアです。UIは、自作フレームワーク「Focus」を用いて、画面ごとにビューコントローラを切り替える方式で構成。開発元は、この仕組みを活用できるSDKをオープンソースとして提供する予定で、読書アプリにくわえて、各種Eインクガジェットのプラットフォームとして使える構想。
特に注目すべきは、バッテリー管理と拡張性です。市販のリーダーではブラックボックスになっている回路図やKiCad形式の設計データを、開発元は製品出荷時にすべてオープンソースライセンスで公開する計画だそうです。そのため、ユーザーは故障時の修理や改造を、3Dプリンタなども用いて、自分の裁量で自由に行えます。
Open Book Touchは、AmazonのKindleストアや楽天Koboストアで購入したDRM付き電子書籍を、通常使用でそのまま読むことは想定していません。なので、本機がターゲットとする対象は、DRMフリーのEPUB/PDF形式で配布しているO’Reillyなどの技術書や、青空文庫、自炊したPDFデータやドキュメントなどを管理したいエンジニアやDIYを楽しむ層です。
標準ファームウェアでは基本的な読書機能が提供されますが、CircuitPythonやArduino IDEを用いて、「自分だけの機能」を追加できます。例を挙げると、天気を表示する、カレンダーやタスク管理、ダッシュボード表示、Web上から毎朝のニュースをChatGPTのAPI経由で自動取得する……といった機能を実装できる点が最大の魅力と言えます。
なお、Open Book TouchはESP32-S3ベースのマイコンボードであり、ArduinoだけでなくCircuitPythonなどの軽量なPython実装を動かすことも可能です。ただし、あくまでマイコン向けに機能を絞った実装であり、PC向けのPython環境とは別物です。PyTorchやNumPy、Pandasといった標準のPythonライブラリをそのまま動かすことはできず、GPUや数GB単位のメモリを前提とした重い処理には対応しません。
一方、KindleやKoboはあくまで一般向け家電として設計され、root化や大幅な改造は公式サポートの対象外です。
さらに、ハードウェア面の比較では、Open Book Touchは画面サイズが4.26型と小さく、解像度も219ppiと、数字だけ見ればKindleやKoboの主力機種より一段低い立場になります。
ただし、本体の小ささと軽さは大きな利点です。ポケットに入れて常に持ち歩く用途や、立ったまま片手で読むシーンでは、Open Book Touchのコンパクトさに魅力があります。その一方で、マンガや図版の多い技術書を読む用途では、画面が広く解像度も高い市販eリーダーの方に軍配が上がります。
ソフトウェアとユーザー体験の面でも、性格ははっきり分かれます。KindleやKoboは、辞書、検索、ハイライト、メモの同期、クラウドバックアップなど、読書体験を支える機能が長年に渡るアップデートでサービスが成熟しています。Open Book Touchは、そうした機能を最初からフル装備するのではなく、コミュニティと一緒に育てていく形のプロジェクトです。「電源を入れたらすぐ続きを読めること」を最優先する人には、市販eリーダーの方が安心でしょうね。
Open Book Touchは、普通の家電としての完成度よりも、「自分の理想の読書端末を自分の手で作る楽しさ」に重きを置いた、いわばぶっちゃけ変態寄りのプロジェクトといえます。電子工作やソフトウェア開発が好きで、ESP32やArduino、CircuitPythonなどに触れている人、自炊やパブリックドメイン作品、技術文書を中心に読む人、DRMに縛られない読書環境を求める人には、非常に魅力的な選択肢になりそうです。
現在、Crowd Supplyのプロジェクトページでは「Coming Soon(近日公開)」となっており、メールアドレス登録による通知を受け付けていますが、価格やキャンペーン開始日、出荷時期などの具体的な情報はまだ明らかになっていません。購入後のサポート体制や長期的なアップデート方針も、市販eリーダーほど読みやすくはありません。興味がある読者は、Crowd Supplyのページでメールアドレスを登録して、キャンペーン開始の通知を待つ形になります。

「Open Book Touch」プロジェクトページ
価格は未定ですが、同プロジェクトがこれまで手掛けてきたオープンハードウェアの価格帯を踏まえると、DIY愛好家でも手を伸ばしやすい水準になることを期待したいところです。
| Open Book Touch | |
|---|---|
| 開発元 | Oddly Specific Objects(Joey Castillo氏) |
| プロセッサ | ESP32-S3(Wi-Fi/Bluetooth対応デュアルコアマイコン) |
| メモリ | フラッシュメモリ16MB、SRAM 8MB |
| ディスプレイ | 4.26型Eインク、480×800ドット、約219ppi、フロントライト付き |
| タッチ入力 | 静電容量式タッチスクリーン |
| ストレージ | microSDカードスロット(電子書籍などを保存) |
| バッテリー | 1800mAhリチウムポリマー(ユーザー交換可能) |
| 端子 | USB Type-C(充電・データ転送) |
| 本体サイズ | 高さ118mm、幅77mm、厚み9.6mm |
| 重量 | 約85g(3Dプリント筐体込み) |
| 筐体 | 3Dプリント対応ケース(設計データを公開予定) |
| ソフトウェア | ESP-IDF+FreeRTOSベースの独自ファームウェア、Arduino/CircuitPython対応 |
| 発売状況 | Crowd Supplyでクラウドファンディング準備中(Coming Soon) |