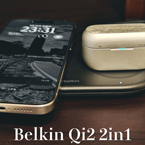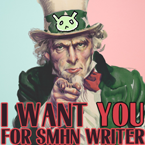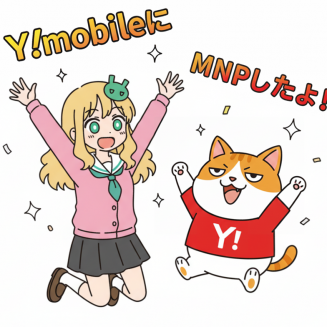画像出展:東京大学
東京大学は、一回のフル充電で一ヶ月以上動作する超低電力の指輪型無線マウス「picoRing mouse」を開発しました。指に装着する小型デバイスで、ARグラスなどと組み合わせることで、日常空間での目立たない入力インターフェースとして使うことを想定しています。
指輪部分の消費電力はおよそ30〜500マイクロワットとされ、世界で初めてマイクロワット級の無線通信技術を指輪型デバイスに導入した研究だと説明しています。
研究グループは、東京大学大学院工学系研究科の高橋亮特任助教、川原圭博教授、染谷隆夫教授、横田知之准教授らによって構成されています。従来の指輪型デバイスは、小型電池しか積めず、BLE(Bluetooth Low Energy)のような低電力無線を用いても1〜10時間程度で電池切れになることが課題でした。
そこで本研究では、指輪の近くに装着するリストバンドを中継器として活用し、指輪とリストバンドの間をつなぐ「磁界バックスキャタ通信」を新たに開発。通信システムの消費電力を従来の約2%まで削減し、長時間駆動を実現したとしています。
磁界バックスキャタ通信は、本来NFCなどで利用される技術ですが、従来は無線給電も兼ねるコイル設計のため通信距離が1〜5cm程度に限られていました。picoRing mouseでは、分散コンデンサを用いた高感度コイルとバランスドブリッジ回路を組み合わせることで、この通信距離を指輪とリストバンドの間である12〜14cm程度まで拡大。指輪側の無線信号を増幅せずに中距離通信を成立させた点が技術的なポイントです。
東京大学は、picoRing mouseとARグラス、リストバンド型デバイスを組み合わせることで、屋内外を問わず、いつでもどこでもARインタラクションが行えるようになると期待を示しています。電車内や街中などでも、周囲の目をあまり引かずに、自分の目の前に浮かぶ仮想画面を自然な指の動きで操作できる未来像を描いています。

画像出展:東京大学