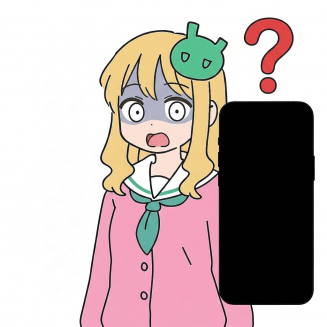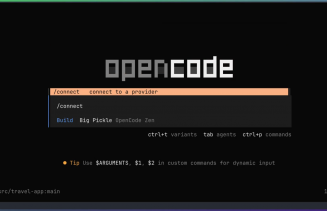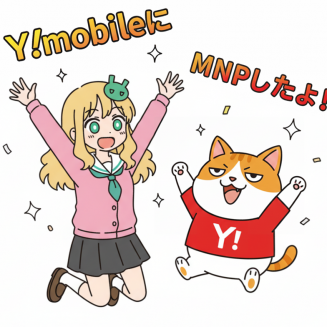スマートフォンのデザインがどんどん変わっていく中、長い間デザインに大きな変化のなかったXperiaですが、今夏のXZ2では背面のデザインが大胆に変更されました。
「Xperiaのデザインはカッコいいのか?」というと個人の好みの問題ではありますが、中国で「いつからソニーのスマホはカッコよくなくなったのか?」という論評記事が紹介されていたため、ご紹介します。
ダンベル扱い。XZ2の与えた衝撃
今年2月のMWC2018でソニーはXperia XZ2を発表しましたが、これを受けてソニーのスマホがダサくなった、という話がソニーファンの口から出始め、これは他のブランドのファンがケチをつけるよりも多いと切り出し、以下のようなあだ名がXperiaに付くようになったと伝えています。
すぐに珍しいほどの勢いで悪評がかけめぐった。その中には、ソニーのスマホを長年使用し続けてきた忠実なファンも多く含まれる。一夜にしてソニーファンが大挙逃げ出すスローガンとなったのが「索半斤」「健身器材」だ。
「索半斤」は「ソニーのダンベル」、「健身器材」は「健康器具」という意味で、ともに中国でつけられたXperia XZ2のあだ名です。XZ2シリーズはかなり重量があるためこのようなあだ名で呼ばれているのでしょう。のっけからボロクソですが、まだ続きます。
我々はソニーがベゼルレスディスプレイで遅れているのを嘲笑し、ソニーの滑らかではないフォルムを嘲笑し、ソニーのデコとアゴを嘲笑しているが、昔のソニーのスマホは、ずっと強烈なデザイン存在感があった。しかしXperia XZ2発表後、みなが見たのはHTCが生んだ背面デザインだった。ソニースマホは最後のこだわりまで消耗し続けてしまったのだろうか?
別れたあと、ソニーが出した答え
日英合弁会社Sony Ericssonは、2012年に100%子会社化されSony Mobileとなりました。
2012年初にエリクソンと正式に袂を分かった後、多くのソニーの昔からのファンたちは、新機種のデザインを首を長くして待っていた。完全な日系の血統に戻った後、ソニーの新機種は完全に日本のチームが設計を担当することとなり、日本の設計チームはXperia arc (LT15i)と Xepria ray(ST18i)の実績があったことから、その後のソニーが最初にどんな純日本式デザインを出すのか、期待させられずにはいられなかった。
 編集部補足
編集部補足確かにXperia arcは斬新で素晴らしかった。画面消灯時にかっこいいクリアブラックパネル、スマホへの採用としては当時の先駆け。 弓を引く時をイメージしたアーク形状。当時のXperiaのデザイン言語であるヒューマンカーヴァチャーは多くのユーザーを魅了した。小型機Xperia rayも懐かしい。まだ持っているが今でもたまにメディアプレイヤーとして使ってあげたくなる。rayは後のXperia SXに続く。
Xperia S(LT26i)がソニーの出した答えだった。この答案は完璧ではなかったかもしれないが、しかし絶対に見るべきものはあった。クリスタルラインのデザイン(フローティングプリズム)だ。
クリスタルラインはXperia S、Xperia P(LT22i) と Xperia U (ST25i)でまったく同じように使用され、Xperia SP(M35c)では位置が微妙に変更された。
ソニーのスマホは一貫して、デザイン重視手触り軽視の感覚がある。Xperia Sも手で持った時のフィット感がいいモデルではなかった。触ったことがある人なら覚えているとおり、Xperia Sは背面に一定の湾曲があるものの、玉石をモチーフにした造形のGalaxy S3と比べると、Xperia Sは四角張ったスマホだった。
四角張ったデザインで最も直感的なところは、 Xperia Sの厚さは10.6 mmにもなった。Galaxy S3 は 8.6 mm,iPhone 5 は 7.6 mmだった。並べてみるとカッコいいが、持ち心地はよくない、これはソニーのスマホが数年間持ち続ける通弊にもなったようだ。
 編集部補足
編集部補足Xperia Sは国内ではXperia NXとして発売された。やや重たく、魅力としてはXperia Pなど国際版モデルの方が上回っていたと記憶している。Xperia NXはフローティングプリズムが単なるデザイン的な象徴でしか無かったが、Xperia Pはアルミ筐体であるため、フローティングプリズムというパーツが電波感度を高める役割を担うと同時に、ここがナビゲーションキーとしても機能するなど、デザイン的な完成度はXperia Pが高い。
2012年9月、下半期に入ったソニーは慣例上フラッグシップモデルを発表し、前後2年間とリンクさせる。ソニーは再度新設計を繰り出し、筆者が個人的にとても好きだった Xperia TX(LT29i, 国内ではXperia GX)が大衆の眼の前に登場した。全平面時代が来る前、Xperia TXはソニーエリクソン時代への短い「文芸復興」だった。Xperia arcの曲線デザインが、再びソニーのスマホに舞い降りたのだ。
 編集部補足
編集部補足GXと同時期に出た、重量わずか約95gのXperia SXも印象深い。このあたりのモデルからミュージックアプリは「Walkman」の名称を冠し、「いよいよS-Master搭載か、次はカメラ事業部全面協力で特製カメラモジュールでCyber-shotも取り込むのか」と期待に胸を踊らせたものだ。驚くべきことに、6年経った今、ようやく今になってカメラ部門全面協力で一新されたカメラモジュールがXZ2 Premiumに載ったところなのだが。
Xperia TXの背面を上に向けて机の上に置いたとき、その背部に凹みのある曲線デザインに気付くはずだ。この湾曲を「アーク曲線」と呼ぶ。ソニーエリクソン時代のXperia arc(LT15i)にもあった。
Xperia TXへの愛着は、 Xperia arc への懐かしさから来たものであり、ゆえにこのスマホの存在感は少し弱かった。しかし2012年にソニーのスマホデザインは大きな変化を迎え、しかもそれは天馬が空を駆けるような創造力を有したものだった。
成功しても全平面、失敗しても全平面

(Xperia Z)
2013年はソニーのスマホにとって、記録されるべき意義のある一年だった。Xperia Z (L36h)が切り拓いたOmni Balacne全平面デザインの時代は、ソニーがこの数年間の設計で練りに練った、高度に伝承性と認知度を具えた設計理念だった。
Xperia Zは衝撃的でしたね。1枚ガラスのディスプレイと透き通るような背面、本当にかっこよかったです。
 編集部補足
編集部補足VAIOのクリアブラックパネルを採用し、画面消灯時は前面ベゼルが一体化、1枚のガラスと化すデザインを採用してきたXperiaシリーズの、たどり着いた一つの答えがXperia Zだったのではないか。スマホは突き詰めれば一枚のガラスの板になる、少なくとも5年前のXperiaは未来を見通していた。
全平面をどう理解すべきか?全平面デザインはソニーのスマホが心血を最も注いだ設計言語であり、とても野心的な挑戦だった。全平面デザインの重点は上下左右前後内外対称のデザインであり、デザイン元素の対象ではなく、設計理念の対称だった。
ソニースマホの北京/台北設計総監だった勝沼潤氏はインタビューで、「Xperiaを設計した際に採用したのは、平板の設計理念だった、平らで四角いのが更に尖鋭となった。しかしXperia Z1(L39h)になると円角デザインを設計に取り入れ、ボディを安定させて、スマホが手から滑り落ちにくくした。これは一種のバランスだ」と答えた。
 編集部補足
編集部補足パスポートサイズで独自路線開拓を試みるファブレットXperia Z Ultraも懐かしい。Xperia Z1はGレンズ搭載を謳うもカメラのソフトウェアはダメダメで、カメラソフトの完成はXperia Zシリーズのひとつの頂点であるXperia Z2の登場を待つことになる。国内ではキャリア3社からも同時投入され、キャリアロゴの煩さの無くなったXperia Z3の印象が強いかもしれない。
Xperia Z1が発表された時、当時の平井一夫SEOは発表会で「One Sony」の概念を宣言した。ソニー各部門間の協業から優秀な製品を作り出そうというものだが、そのあとソニーがベゼルレスディスプレイの進展が遅れたのと一定の関係があるのかもしれない。
これも2013年から、「画面占有率」という言葉がSNSで多く見られるようになり、大画面で本体の小さなものが優れたデザインと見做されるようになった。その後の「ベゼルレスディスプレイ」とはこの理念の延長にほかならず、この設計思想は数年後に市場を完全に支配した。このとき、ソニーは「取り残され」はじめる。
著者が何をもって「One Sony」とベゼルレスディスプレイへの乗り遅れを関連付けているのかは必ずしも明らかではありませんが、ソニーの他製品のデザインとの統一性も、もしかしたら関係があったのかも?
 編集部補足
編集部補足ソニーは映画も手がけており、それが頑なに動画主流の16:9比率に画面を維持させるに至った、という考察だろうか?

(One Sonyのスローガンを掲げた当時の平井一夫社長)
それにしても、Xperia Zと「画面占有率」概念の登場がほぼ同時期というのは、今から見ればなかなか皮肉ですね。当時革新的なデザインだったXperia Zと、それを後に「古臭くさせる」概念が同時に登場していたとは。
しかし多くの人が見逃しがちなのは、最初の全平面設計のスマホ Xperia Zには「弟」があった——Xperia ZL(L35h)だ。フラッグシップのXperia ZL はソニーの画面占有率路線での、一つの試みだった。75%を超える画面占有率は当時世界一だったが、Xperia ZL の販売台数と影響力は、悲惨なものとなった。
或は、ソニーの全平面設計路線が固まったのには、 Xperia ZLの失敗も理由の一つだったのかもしれない。
Xperia Z から Xperia Z5 Premiumまで、初代から最高傑作まで6代のフラッグシップ、Premium 版なども含めると14モデルのフラッグシップ級すべてで全平面設計が採用された。そのなかでも、 Xperia Z5 Premiumは特筆すべきモデルだ。
 編集部補足
編集部補足この時点での4K搭載はコンテンツに乏しく実用性はあまり無かったが、技術のデモンストレーションとしては面白かった。
Xperia Z5 Premiumは全平面設計最後のモデルであり、最高傑作でもある。細部の設計はこれまでの粋を集めたものと言える。もっとも魅力的な部分の一つは背部の鏡面設計であり、シルバーカラー版の平らな鏡面は、Xperia Z5 Premium の背部を窓となし、全ての世界を中に含んでいるようだ。
鏡面も魅力的だが、ファンを最も魅了する部分ではなかった。ファンが最も「信仰」を燃やすのは、ボディ側面に刻印された「XPERIA」の文字だ。
しかし「なんとかの一つ覚え」ともいうように、Xperia Z3+以来、同じような設計が飽きられていた。さらに各種の原因で連年の赤字、販売額の下降。全平面時代後期のソニーは、英雄の末路に失望させられるような感覚があった。新モデルは依然としてカッコよかったが、しかし時代は既にソニーのものではなかった。
 編集部補足
編集部補足Xperia Z3+は、日本国内ではXperia Z4として登場した。Xperia Z4とZ5は爆熱プロセッサーSnapdragon 810を搭載していたため、熱やパフォーマンス維持、電池消費などに不評も多かった。
登場当時はその運動性能から不敗神話を築き、一世を風靡した零式艦上戦闘機「ゼロ戦」も、空中戦の戦法が「巴戦」から「一撃離脱」、求められる性能も運動性能から速度へと移り変わったにもかかわらず、後継機の開発が遅れたことから生産が続けられ、最後は特攻機に使用されたのと似たものを感じます。
2016~2017年
Xperia Z5 Premiumが全平面時代の頂点となった後、既になんの新味も出しようがなくなったと感じさせた。打つ手のなくなったソニーはついに設計言語を転換し、さらに名前の上でも全平面よりさらに広い概念となった。新しい設計言語は「一体化」設計と呼ばれた。
初期の一体化設計は完成したものではなく、2016 年初に投入されたXperia X Performance と Xperia Xは過渡期にあたる。
 編集部補足
編集部補足国際発表では「継ぎ目のないデザイン」を謳ったSony Mobileだったが、国内モデルではアンテナ感度を確保できず最下部に大きな継ぎ目が配置され、一部のユーザーからは「おむつ」の名称で揶揄された。
全平面時期のガラスボディは メタルボディに置き換えられ、ベゼルまで延長された。Xperia XZは一体化設計の完全体となった。
 編集部補足
編集部補足XZでは、グローバル版も含めてX Performanceのようなアンテナが下部に設けられた。
しかし、この一体化設計かソニーに捲土重来の機会を与えなかった。旧態依然とした広い「デコとアゴ(上下の極太ベゼル)」は、変わり映えのしない印象を与えた。ここからソニーは、完全な「信者ビジネス」になった。
以後、2017年はXZから代わり映えのしないXZsとXZ1が投入。
 編集部補足
編集部補足この頃にもなるともはやミッドレンジ帯においても生体認証が当然のものとなる。だがXperiaは、実は米国市場では特許の問題から側面の指紋認証センサーを無効化して出荷していた。
2017年はベゼルレスディスプレイが急速に発展した1年になった。しかしMWC 2017で、Sony MobileのDon Mesa氏は「主流娯楽との兼ね合いもあり、ソニーはベゼルレスディスプレイの発展に注力することはない、少なくともそんなには早くならない。ソニーは映画会社でもあり、部門の間で相互に排斥することはない」と述べた。まさか、足を引っ張る時にだけ「One Sony」を思い出すのだろうか?
 編集部補足
編集部補足画面比率が16:9のまま保守的である言い訳を映画部門に求めたことを記事は批判的に見ているようだ。
ファンまで嫌うように
そして2018年、MWC2018においてXperia XZ2シリーズが発表。新しいデザイン言語Ambient Flowによって、デザインを刷新しています。

(Xperia XZ2 画像出典:Android Authority)
ついに18:9ディスプレイを採用したにもかかわらず、設計の決定的失敗となった。
カクカクした元素と勢いのあるラインこそ、ソニーの近年の設計上、最も直観的な要素だった。それがAmbient Flowはソニーに丸っこい3D曲面のガラスと曲線、さらに弧状のガラス背面をもたらし、我々のイメージするソニーとは正反対な、奇妙な現象を作り出した。
ソニーの忠実な信者はソニーの「裏切り」と見做し、ソニーファン以外は「HTCのパクリ」と見た。しかも、かつては「軽薄」を追求したソニーが、Xperia XZ2 Premiumでは努力を放棄して「ダンベル」となり、筆者の友人のソニーファンはこのモデルを手にした後「健康器具だ、ご理解を」というのが口癖になった。
今回、ソニーファンまでソニーを見捨て、とんでもなく重鈍なXperia XZ2 Premiumには強い嫌悪感ばかりとなった。
デザインには様々な評価、感想があるでしょうが、筆者がとても怒っているのは伝わってきますね。なお、私はXperiaの背面は平面でないと認められない派です。
 編集部補足
編集部補足あらゆるタイミングが致命的に噛み合っていないのではないだろうか。米国市場で電源ボタン一体型指紋認証センサーが利用できない兼ね合いから、変更しなければならないのはわかるが、側面指紋認証センサーは一定の評価を得ていたわけだから、顔認証・画面内指紋認証センサーの搭載を以て初めて廃止すべきだった。「Ambient Flowがダサい」はまだ個人の感性の違いで済ませられる余地もあるかもしれないが、「押しにくい場所に指紋認証センサーを押しやったAmbient Flowが嫌い」は無視できない。また、イヤホンジャック廃止については、5年以上前からNFCと無線機器に取り組んできたソニーグループとして率先してもっと早い段階で廃止しておくべきだった。2016年と2017年、守りの姿勢で守りきれず、尻に火がついた2018年、デザイン変更案を一挙にぶちこみ、奇怪で整合性のないデザインのXZ2シリーズが生まれたのではないか。
Ambient Flow 流体設計の評判が悪すぎれば、ソニーはXperia XA2 Plusで再度一体化設計にもどり、18:9ディスプレイを搭載するかもしれない。それがソニーが瀬戸際で引き返すポイントになるかはわからない。しかし、ソニーモバイルは、既に再度の失敗に耐えることができないだろう。
そういえば、Xperiaはすでに一部海外市場から撤退とも噂され、もう「後がない」のかもしれません。その段階でのデザイン変更、結果的に中国のソニー信者は激怒のようですが、日本市場ではどうでしょうか。以上、中国のソニー信者の怒りをお伝えしました。
このXperia評に https://t.co/lZi4IUxoxq
— すまほん!! (@sm_hn) 2018年7月25日