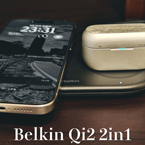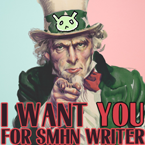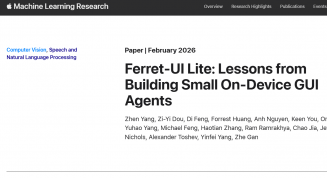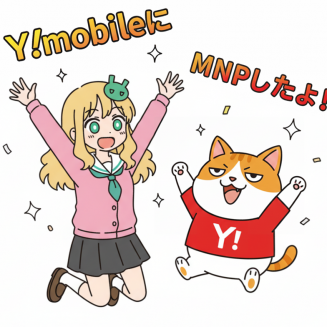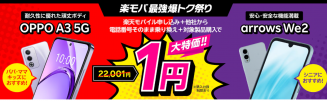Boseから発売された最新フラグシップTWS、QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代)を購入しました。第1世代と比較して、音質、ノイズキャンセリング等の変わったところをチェックしたのでレビューしていきたいと思います。
開封・付属品
Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代)は、2025年8月7日発売、価格は3万9600円と第1世代から据え置きです。
それでは、早速開封していきます。外箱はコンパクトで、左下にこっそり2nd GENが付け加えられています。中身を取り出すと白いシンプルな箱が入っています。この点は第1世代と同じですね。

白い箱の中には、本体・充電ケーブル(USB-A to C)・イヤーチップ・スタビリティバンド・取扱説明書が入っています。

充電器本体は第1世代と比べても外見に違いはほとんどありません。Boseのロゴが少々大きくなっているぐらいでしょうか。ただ中身は大きく変わっており、第2世代の充電器本体は最初からワイヤレス充電に対応しています。

左が第1世代、右が第2世代
イヤホン本体は第1世代と比べても形状はほぼ同じです。

左が第1世代、右が第2世代
イヤーチップは第1世代と比べて新調。耳垢がイヤホン本体に入りにくいように、フィルターが追加されました。

イヤーチップのサイズはS・M・Lの3ペアがあり、最初から装着されているのはMサイズです。スタビリティバンドに関しては1・2・3の3ペアがあり、最初から装着されているのは1サイズです。

装着感
本機のイヤホン重量をイヤーチップなしで計測したところ、6.7gでした。一方で第1世代の重量は6.8g。ほとんど変わっていませんね。

第2世代の重量

第1世代の重量
この価格帯のTWSは最近だとイヤーチップ込みでも6gを切るものも多いので、若干重めです。
しかし、装着感は抜群によいです。装着しながら体を動かしたり、頭を振ってもイヤホンが外れそうになることは全くないです。重量バランスが綿密に計算されているのでしょう。それでいて、簡単に装着でき、ベストポジションにすぐ収まってくれます。このあたりはBoseの蓄積された技術が活きていますね。第1世代からフォルムが変わっていないことから、この形状でほぼ完成形なのでしょう。
音質
「これぞBoseサウンド」と言える、重厚で迫力のある低音が特徴です。しかし、昔の低音重視イヤホンにありがちな「ぼわついた低音」ではなく、しっかり引き締まって中高音域を邪魔しない、上質な低音に仕上がっています。また、低音の質が向上しただけでなく、中高音の解像度もわずかに上がっているように感じました。
実際、第2世代を聴いたあとに第1世代を聴いてみると、こんなに低音ボワついてたっけ?と感じるほどに迫力・解像度ともに進化は感じられました。
Boseアプリを使うことで、低音・中音・高音の調整が可能です。低音や高音を強くしすぎても音割れしないので、良質なイコライザだと感じます。ただ、ここ最近のTWSは更に細かい周波数で調整できるイコライザを備えているので、それと比べると簡易的です。

第2世代で色んなジャンルの音楽を聴いてみましたが、どのジャンルも良い意味で迫力を演出してくれるので、これ一つ持っておけば幅広く聴けると思いました。敢えて得意ジャンルを挙げるとすれば、ロック、電子音楽ですかね。強いて苦手ジャンルを挙げるならば、ピアノや静かめの音楽でしょうか。
最近流行りのイマーシブオーディオ(AirPodsでいう空間オーディオ)という機能も続投しており、これをオンにするとあたかもライブ会場で聴いているように立体的な音響を体験できます。ただ、こちらをオンにするとバッテリー消費が早くなり、個人的に音質がかなり不自然になると感じるので、私は常にオフにしています。
ちなみに筆者は音質に定評のあるEAH-AZ100も所持していますが、やはり細かい表現力はEAH-AZ100の方が上でした。ただ、ノリよく音楽を圧倒的な静寂で聴くという点ではBoseに軍配が上がります。EAH-AZ100とはターゲット層が異なり、比較する人はあまりいないかもしれませんが、参考までに。
ノイズキャンセリング
ノイズキャンセリング機能は、電車内と賑やかな繁華街の2か所で、第1世代モデルと比較してテストしました。テスト中は、音楽を流さず無音の状態にしています。
まず、電車の社内ですが、電車の走行音は両者ともにかなりカットされています。ただ、車内のアナウンス音は第2世代のほうが体感カットされている印象でした。
次に、賑やかな繁華街ですが、人の声といった中高音域のカット率が第2世代では体感上がっていると思いました。第1世代では、繁華街での騒ぎ声が耳障りに感じることが多かったですが、第2世代ではカット率が上がり、少々マシになっている印象です。なので、カフェ等のあまり大きな声がしない場所で第2世代を使えば、かなり集中できるのではないでしょうか。
ノイズキャンセリングの強度についてまとめると、第1世代の時点でノイズキャンセリングに関しては全TWS中最強に君臨していましたが、第2世代で低音域のカット率はそのままに、中高音域のカット率が更に強化されました。ただ、第1世代の時点でかなり強いノイズキャンセリングを搭載しているので、公式が謳う、”ワールドクラスのノイズキャンセレーション”を真に受けて、圧倒的な進化を期待すると面食らうかもしれません。
また、Boseアプリを使うと、ノイズキャンセリングの強度を10段階で変えることができ、プリセットとして保存しておくこともできます。普段はノイズキャンセリングを最大にしておき、人と話すタイミングでノイズキャンセリングが最低のプリセットにイヤホンのタッチ操作で変更することも可能です。

ノイズキャンセリングの他にも、イマーシブオーディオのオンオフや、プリセットの名称も変更できる
一方、アウェアモード(外音取り込みモード)にしておくと、周囲の音に合わせてノイズキャンセリングの調整を行うActiveSenseというモードが使えます。ただ、使ってみた印象としては、あまり恩恵を感じませんでした。外音によってノイズキャンセリングが変化するタイミングで自律神経が狂い、酔ったような感覚になるので、私は使っていません。
操作感
操作感は第1世代から変わっていません。率直に言うと不便さが解消されていません。
第1世代から続投で、シングルタップで音楽停止、ダブルタップで次のトラックへ移動、トリプルタップで前のトラックに移動、長押しで上下スライドで音量の上下、長押しで任意のアクション(ノイズキャンセリングモードの変更、Bluetoothソースの切り替え等)にアクセスの5つの操作が可能です。
こちらの機能ですが、シングルタップしたつもりがスライド認識されて音量が変わったり、ダブルタップしたつもりがシングルタップ認識されて音楽が停止するといった誤認識が結構発生します。歩きながらで手がブレる状態でタップすると、更に誤認識する頻度が上がります。
手持ちのEAH-AZ100ではタップの誤認識は起こりにくいので、このあたりは単純にチューニング不足だと思います。
また、EAH-AZ100ではアプリでシングルタップやダブルタップの割り当てを変えることができるのですが、本機は固定で変えることができません。タップの割り当てを変えたい方は注意です。
マルチペアリング
本機にはマルチペアリングが搭載されており、最大2台まで同時接続可能です。結論から言うと少々不安定ですが、便利に使える機能だと感じました。
実際に所持しているM4 Mac miniとGalaxy Z Fold6をマルチペアリングしてテストしてみました。この状態でMac miniで再生しているメディアを止め、Z Fold6でメディアを再生するとシームレスに切り替えが行われました。ただ、たまに一方の端末に再生が集中してしまい、シームレスに切り替えが行われないことがありました。この点は少し不安定だと思います。
また、他機種(EAH-AZ100)では、一方でメディア再生すると、もう一方でメディア再生中だとしても強制的に切り替えになりますが、本機では切り替えになりません。一方のメディアを停止してからもう一方のメディアを再生する必要があります。ただし、着信があったときは、一方でメディア再生中でも強制的に切り替わりになります。どちらが便利かは一概に言えませんが、個人的には一旦停止する手間が省けるので、EAH-AZ100の方式だったら便利だったなと思っています。
接続安定性
接続安定性については、閑静な住宅街、乗車率150%程度の電車、阪急うめだ本店コンコースという、混雑度の異なる3つの場所で音楽を聴き、接続の安定性を検証しました。阪急うめだ本店コンコースは、常に人が多くTWSの接続が途切れやすい場所として選んでいます。
結論としては、上記のどの場所でも接続は途切れず快適に音楽を聴くことができました。第1世代も当初は、阪急うめだ本店コンコースで接続途切れが発生していたのですが、アップデートで改善し、全く途切れなくなりました。その技術が第2世代でも活かされているのでしょう。
総評
以前は、BoseのTWSはノイズキャンセリングは最強だけど、音質は同価格帯のソニーやTechnicsと比べるとこもり気味…ということがありました。ただ、今回のQuietComfort Ultra Earbuds 第2世代で、迫力・解像度が改善し、完成度が高まりました。
この圧倒的なノイズキャンセリングによる静寂で、迫力のある音楽を外で聴けるというアイデンティティは唯一無二です。
操作性・接続に若干の問題があるものの、外出時にリスニング用途で使うならばこの価格帯で十分お薦めできる一台だと感じます。機会があれば、ぜひ視聴してみてください。