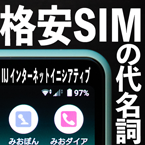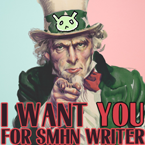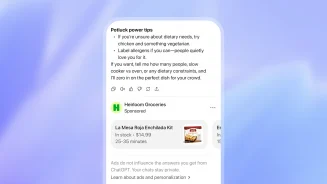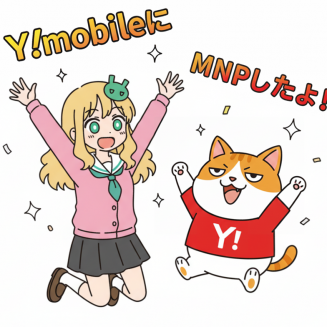マイクロソフトは、光とアナログ電子回路を融合させた新型コンピュータ「アナログ光コンピュータ(AOC)」に関する研究成果を科学誌「Nature」で発表しました。金融と医療の実データで有効性を示しつつ、将来はGPU比でエネルギー効率を100倍以上に高める可能性を示したといいます。
このアナログ光コンピュータは、光学とアナログ電子回路をフィードバックで結び、固定点探索として計算を統一する設計によって、一台のハードウェアで「AIモデルの推論」と「組合せ最適化」という、性質の異なる二つの計算タスクを両立した点が最大の特徴です。
従来のアナログコンピュータや光コンピュータは、どちらか一方のタスクに特化していましたが、マイクロソフトのアプローチは、共通の計算原理を用いることで、この汎用性を世界で初めて実現したといいます。
「AIモデルの推論」は、学習済みモデルに新たなデータを入力して結果を導く計算処理で、「組合せ最適化」は、選択肢の組合せの中から最適な解を見つけるための計算手法です。
具体的には、過去のデータから学習したパターンに基づいて、未知のデータに対して「何か」というのを予測・分類するのがAIモデルの推論です。ざっくりたとえると「この写真に写っているのは、学習したパターンからすると猫の可能性が高い」というように、知識や経験に基づく直感的な判断に近いです。
一方、組合せ最適化は、「ある条件下で、どのような組合せが最適なのか」を求める計算です。「全てのルートを検討した結果、この道順が最短時間で配達できる唯一の答えだ」というように、論理的に最善手の組合せを求める計算です。
さらに言えば、たとえば不動産を鑑定評価する場合、AIモデルの推論は過去から現在にかけて最有効使用で稼働している類似物件の取引事例を参照し、補正を加えて価格を導く「取引事例比較法」に近いといえます。
それに対し、組合せ最適化は、対象不動産に対して、法的・物理的・経済的な条件を考慮しつつ最も合理的かつ収益性の高い用途、つまりは最有効使用を判定する分析プロセスに対応するものと考えられます。
「なぜ、ここでいきなり不動産の鑑定評価のたとえ話を持ち出してきた?」と思われたかもですが、それは筆者自身がいま現在不動産鑑定士試験の勉強中で、この分野にも当てはまる話では、と思ったからですね。唐突で申し訳ありません。

論文には実問題の検証として金融大手のBarclaysと協力し、受渡同時決済(DvP)の決済選択問題にAOCを適用し、多数の取引を効率的に決済する問題を解決したとあります。また、医療分野では、MRIスキャンの画像再構成にかかる時間を、理論上30分から5分へと約6分の1に短縮できる可能性を示しました。これらは、アナログ光コンピュータが現実世界の問題に対して、実用的な解を提供した初めての事例となります。
光の速度と並列性を利用する光学系と、複雑な非線形処理を得意とするアナログ電子回路を巧みに組み合わせたハイブリッド構成の仕組みによって、計算のループ内では、デジタルとアナログの信号変換を徹底的に排除してエネルギー効率を大幅に高めたとのこと。いわゆる「フォン・ノイマン・ボトルネック」と呼ばれるデータを行き来させる手間を回避できるため、処理の遅延も大幅に削減されるという見込みです。

Nature 論文「Analog optical computer for AI inference and combinatorial optimization」Figure 1(a–c)
マイクロソフトの試算によれば、この技術が将来的に専用ハードウェアとして集積化された場合、エネルギー効率は1ワットあたり約500兆回(500 TOPS/W)に達する可能性があるとしています。これは、現在最先端のGPUと比較して100倍以上も効率的な数値であり、AIの運用に伴う莫大な電力消費という、現代社会が直面する大きな課題への解決策となり得ます。
現在のプロトタイプはまだ16変数という小規模なものですが、「時分割」という技術を用いることで、より大規模なモデルの動作にも成功しています。今後は、光学素子とアナログ回路をより高密度に集積化することが大きな課題となりますが、数年前からムーアの法則の限界が指摘されて久しい中で、このアナログ光コンピューティングは、デジタル技術の進化の希望の光となり得る、極めて重要な一歩と言えるかもしれません。
マイクロソフトは、研究を加速させるため、このコンピュータの動作を再現するソフトウェアシミュレータ「デジタルツイン」や、最適化問題を記述するためのパッケージをGitHubなどで公開しており、今後の技術の発展とエコシステムの形成が期待されます。