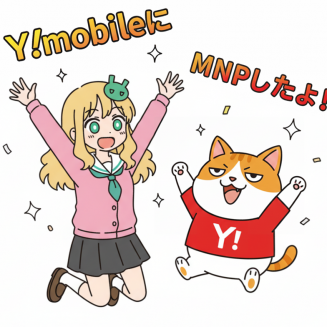米トランプ政権により、次から次へと「制裁」と「排除」が実施されている、中国華為(Huawei)ですが、中国国内では、映画にもなった朝鮮戦争での中国人民志願軍と米軍との戦闘になぞらえ「これは最先端技術の”上甘岭戦役”だ」と呼ばれ、そして18万人の華為社員を「英雄児女」と、これも朝鮮戦争もの映画タイトルで賞賛されていることがわかりました。

(上甘嶺の戦い、DP28軽機関銃で米軍と戦闘する抗美援朝志願軍兵士)
赤峰市中国共産主義青年団(年齢10代・20代の加入する共産党の下部組織)の微博公式アカウント「赤峰青春」は5月26日に「18万人の華為『英雄児女』は最先端技術の上甘岭で、米国と死闘を展開している」との文章を発表。気合が入っていて面白いので、まずこちらからご紹介します。
米政府による一連の措置を紹介した上で、次のように華為について述べています。

「前代未聞の封鎖と弾圧に直面しながら。華為の上下全体職員は空前の団結をし、闘志をたぎらせて挑戦を受けている」。
「連日連夜の残業によって夜戦を挑む。海外出張から帰ってきた社員は、まず会社へ駆け戻って仕事をする。海思チップ、鴻蒙OS、華為が長年準備してきた『スペアタイヤ』は一夜にして本物になった。これが華為の士気である」。
「成立から僅か30有余年、華為の征戦は目を見張る成績を収めてきた。2018年の全世界営業収入7212億元、純利益593億元。2018年華為の研究開発費用は1015億元、ここ十年に投入した研究開発費用は4800億元以上。スマホ販売台数2億台を突破、世界第3位。5G基地局7万以上。これが華為の実力である」。
「今、米国は卑劣にも華為に牛刀を振り上げ、華為の発展を断ち、中国科学技術の進展を阻止しようと妄想している。これは新時代の上甘岭だ!」
気合の入った現状説明に続き、ここから「上甘岭」の話に入ります。
「60数年前、抗美援朝(米国に抵抗して朝鮮を援助=朝鮮戦争)の戦場で、勇猛頑強なる中国人民志願軍は敵の一度、また一度と繰り返される侵攻を撃退した。今日、18万人の華為『英雄児女』は最先端技術の上甘岭陣地にて、米国と『死闘』を展開している。60数年前、上甘岭は敵の『傷心岭』となった。今日、新時代の上甘岭は敵の『絶望地』になろうとしている」。
なお、上甘岭の堅塁を米軍側は「鉄の三角地帯」と呼んでいました。
「60数年前の上甘岭戦役の勝利は、正確な決断と指揮、志願軍の勇猛なる戦闘のほかに、全国人民の大きな支持に頼ったものだ。同様に、新時代の上甘岭戦役は、任正非先生の遠謀深慮、18万華為社員の奮闘努力のほかに、国民全体による支持が更に必要になる。この厳しいとき、愛国にかかわらず、商業にかかわらず、ただ尊敬されるべき企業のため、ただ二度とイジメられないとの意志のため、独立自主、艱難奮闘の精神のため、我々は団結し、華為を支持しよう!」
と、アジテーションも高らかに、全国人民に団結を呼びかけています。なお、「英雄児女」と「上甘岭」はともに、米トランプ政権が華為をブラックリストに入れたことを受け、中国国営テレビがゴールデンタイムに放送した朝鮮戦争もの映画。完全に、「そういう文脈」に組み込まれていってますね。
華為の社員をすっかり「対米戦争の兵士」扱いしてしまう向きもあるようですが、実際の華為の社員たちや、その周囲の雰囲気はどのようなものなのでしょうか?5月24日に中新経緯が伝えたところによると、華為の微博公式アカウントが「我々華為人」との題で、社員やその家族からのメッセージを公開しています。
「彼女がケンカをしなくなった、私が安心して仕事ができるように」
「仕事を辞めようとしたら、家族から脱走兵になるなと止められた」
と、こちらもなかなか「戦争」感があるコメントが並んでいますが、なかでもすごいのは、こちらの「華為社員の妻からのメッセージ」。
「私はこの戦役が既に始まり、我々には退路がなく、我々は奮闘努力して必ずやこの戦争を勝ち抜き、世界第一へ向けて前進しなければならない、ということしか知りません。華為の家族として、あなたの銃後として、戦争に臨み存亡の危機にあって、私ができるただ一つのことは、歯を食いしばってあなたの銃後の旗を担い、あなたが何の後顧の憂いもなく全力を仕事に投入、この硝煙のない戦争に集中できるようにするだけです」。
完全に銃後の妻、「気分は戦争」ですね。ここまで話が盛り上がっているのを見ると、最悪、華為にとどまらず、中国各メーカーを巻き込んだ標準規格戦争に持ち込んででも徹底抗戦しそうな気すらしてきます。
平成初期、「貿易摩擦」といえば、米国人に日本車を燃やされたり、米政府に日本の半導体産業を潰されたりでした。中国で過去の戦争もの、民族の危機、といえば「抗日戦争」をクローズアップされてきました。
それが、今回は米国と中国の殴り合いになり、直接弾が飛んでこないので、ある程度安心して見ることができます。見ていて面白いのが半分、先行きが不安なのが半分、というのが正直なところ。