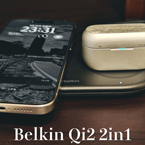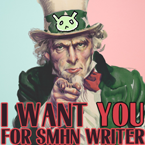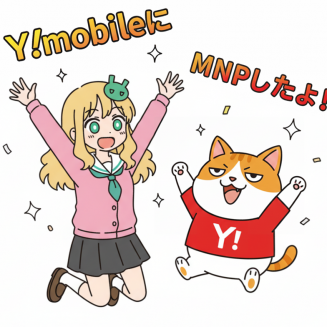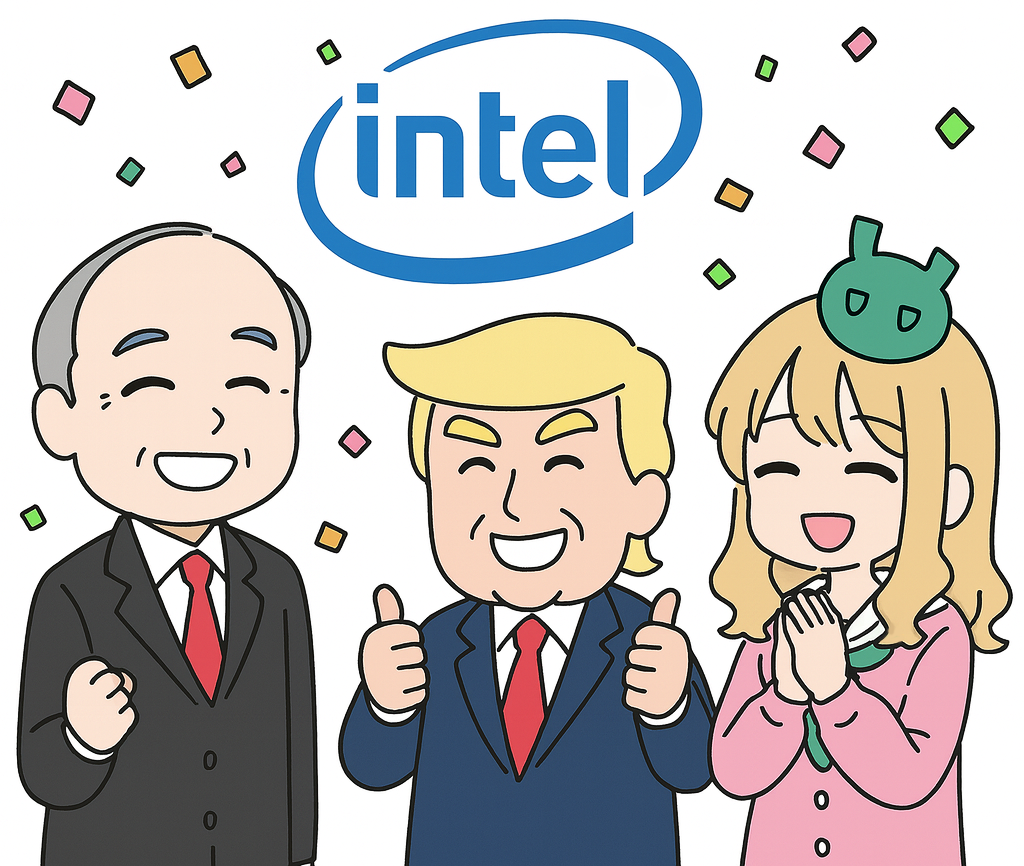
ソフトバンクグループ(SBG)は、2025年8月18日、米半導体大手Intelの普通株に20億ドル(約2950億円)を投資する最終契約を締結したと明らかにしました。これにより、同社はIntelの発行済み株式の約2%を保有し、第6位の主要株主となります。
今回の出資は、SBGが傘下に持つチップ設計の「Arm」に加えて、現在買収手続き中のサーバー向けCPUの「Ampere Computing」と製造の「Intel」との連携を見据えた、設計から製造までの「垂直統合」構想の一環とみられています。Ampereの買収は2025年後半の完了を見込むと発表されていますが、台湾のTSMCが圧倒的なシェアを握る半導体業界の中で、SBGはAIチップの安定供給を目指す狙いがあります。
この動きに呼応するように、米国のトランプ政権もIntelへの出資を検討しているとロイター通信が伝えています。報道によると、政権はCHIPS法に基づく補助金の一部を株式に転換する形で、最大10%の株式取得を協議しているとのことです。現時点で最終合意や条件の確定は伝えられていませんが、もしこれが実現すれば、米国政府がIntelの筆頭株主になり、同社が単なる民間企業ではなく国家的な戦略も担う「国策企業」としての側面がより鮮明になる形です。
株式市場はこの一連の発表に対して好意的な反応で、発表後の取引ではIntel社の株価が一時は12%も急騰しました。民間と政府が足並みをそろえてIntelを支援するこの構図は、米中間の技術覇権争いを背景に、半導体の国内生産能力を強化するという国家目標と一致しており、サプライチェーン再編への強い意志の表れと言えるでしょう。
もっとも、この壮大な構想が成功するには、乗り越えるべき課題も残されています。第一に、技術面の課題です。Intelが次世代の製造プロセスを計画通りに立ち上げ、失われた技術的優位性を取り戻せることが絶対条件となります。第二に、運営面の課題です。これまで自社で設計と製造を完結させてきたIntelが、ArmやAmpere Computingといった文化の異なる企業と連携する中で、スムーズな協力体制を築けるかが問われます。
SBGと米国政府という強力な後ろ盾を得たIntelがこれらの課題を克服できた時場、半導体業界はTSMC一強の時代から、米国を基点とする「Arm」「Intel」を擁するソフトバンクグループの連合軍の新たな連合が覇を競う新時代へと移行するかもしれません。AIにまつわるニュースといえば、ほとんどアメリカや中国の話ばかりなので、個人的に日本発の企業のソフトバンクがこの流れの重要な位置にいるのが胸熱展開で嬉しい気分です。